南アフリカ、ニュージーランド、フランス、オーストラリア、英国代表チームの様なラグビーのトップクラスで誇りを持っているチームは、常に優れたフォワード(FW)プレーを基盤としてゲームを組み立てて戦っています。
FWプレーの中でも、最も重要なプレーがスクラムだと云えるでしょう。
だから、ゲームをコントロールするためには、まずスクラムをコントロールすると云うことが基本的な考えと云えるでしょう。
しかし、スクラムを単なるゲーム再開の一手段と考えている様なチームでは、きっとゲームで好成績を上げることはできないでしょう。
スクラムが如何に重要なプレーで有るかの理由を上げて見ましょう。
(1)攻撃の基本となるのは、ボールを獲得し生きたボールを出すことでしょう。
その点スクラムは、ボールを獲得し生きたボールを出すための最も重要なプレーの一つと云えるでしょう。
何故ならば、第一にスクラムは、ラグビープレーの中で最もFWが組織的に全員の力を集中してボールを獲得し、ボールを出すためのプレーだからです。
第二には、例え相手チームがボールを獲得しようとしても、防御側が最も組織的にプレッシャーを加えるプレーができるからです。
そして、最も体力の消耗の激しいプレーがスクラムだと云えるでしょう。
(2)ゲーム中スクラムは、相当回数(20回前後)組み合うプレーです。
しかも味方ボールで有ればほぼ確実にボールを獲得できる可能性が有り、また相手ボールのスクラムでもプレッシャーを加えて、相手に生きたボールを出させない様に工夫するプレーもできます。
(3)スクラムの好し悪しが、他のプレーに大きな影響を与え、優れたスクラムを組めるチームは、ラックやモールのみならず、サポートプレー、ラインアウト、タックル等の様々な側面のプレーにも優れたプレーを生み出すことでしょう。
これは、第一に優れたスクラムを組むチームは、スクラムでの体力消耗が少ないばかりでなく、スクラムで用いられる基本技術そのものが他のFWプレーの基本に通じているからです。
例えば、押す時の姿勢、足の位置、前進力、力を入れるタイミング、ボールコントロール、そしてその中でも最も重要なものは、FWプレヤー8人が一体となったチームワークです。
スクラムの原理を説明する前に、是非強調して置きたいことが有ります。
それは「優れたスクラムは、十分な練習からしか生まれない」と云うことです。
では十分なスクラム練習とは、一人一人のプレーヤーが筋力やパワーを向上させることも大変重要ですが、それよりも一列の3人、次に5人そして8人全員が一体となった「力」と「タイミング」を得ることが、重要だと云えるでしょう。
従ってシニア・レベルでは、一回の練習につき最低30〜40本のスクラムを組むことが必要でしょう。
スクラムを組む時に、どうしても欠かすことのできない重要項目、即ちスクラムのキーファクターに付いて検討して見ましょう。
スクラムのキーファクターは、フット・ポジション、瞬間の押しとロッキング、力学の3つでしょう。
ア フット・ポジション (Foot Position)
8人のFWプレヤーの16本の足が、それぞれ正しい位置に置かれていなければボールをクリーンに出すことも、押す力を出すことも不可能でしょう。
そして足の位置が正しく無ければ、姿勢もできず後方から加えられてくる押しの力を前方へ正しく伝えることもできないでしょう。
イ 瞬間の押し(Snap Shove)とロッキング(Locking)
瞬間的な押しは、味方ボールに対しては生きたボールを獲得する時、そして相手ボールに対しては相手に生きたボールを出させない様に加える押しです。
ロッキング・スタイルでは、味方ボールを安定して得るために、そして相手の瞬間的な押しに耐えその押しを止めるための姿勢と力です。
ウ 力学(Dynamics)
スクラムに発生する「力」の方向には、3つの種類が有ります。
1つは、水平方向の力。
もう1つは、垂直方向の力。
そして もう1つは、回転力です。
押しの効率を最高にするためには、この様な「力学」を研究し、正しい方向に正しい角度と正しいタイミングで「押しの力」を加えることが大切です。
スクラムの基本と云えば、「姿勢」押しの姿勢でしょう。
スクラムの「押し」は、2つの種類に分ける事ができるでしょう。
その1つは、スクラムを瞬間的に押して味方に生きたボールを獲得する、または相手ボールに瞬間的に押しを加えてスクラムを押し込む「押しの姿勢」。
もう1つは、味方ボールをクリアーに安定させてボールを出すために用いるロッキング・スタイルの「押しの姿勢」。
どちらも、スクラムの基本姿勢であり、ボールを獲得すると云うこと、生きたボールを出すと云うことでは同じです。
[スクラムの基本姿勢]
Snap Shove(瞬間的押しの姿勢)―Locking(ロッキング姿勢)
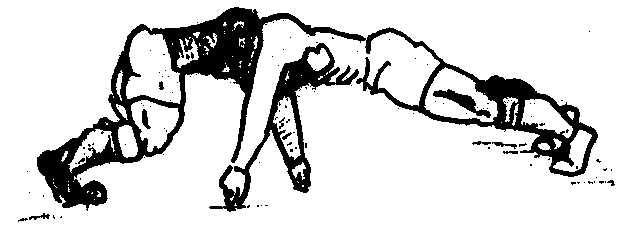
ではFWプレヤー2人で、バランスを取るために片手を地面に接して、一対一のスクラム姿勢で組ませてチェックして見ましょう。
(1)背中と首
両足、胴体そして腕から生まれるパワーは、背骨と肩を通して前の方に伝えられて行く。
そのための必要条件は、まず背中が安定していることが上げられるでしょう。 また背中に加え伝えられた力は、そのまま首に加わり伝えられて行くのです。 ですから首もしっかりと確実に固定されていなければならないのです。
(2)足
優れた押しを加えるためには、両足が後方に置かれていなければならないでしょう。その足を後方でやや開き前後にして置いたプレーヤーと、両足を後方でやや開いて平行に揃えて置いたプレーヤーとを比較して見ましょう。
前者の方は瞬間的な押しに、後者の方は強い押しにたえると云うことが歴然としています。
プレーヤーがまずマスターして置きたい姿勢は、常に両足を後方で平行に揃えて置いた、耐える姿勢でのスクラムを組む方でしょう。
(3)足、腰、膝
足、腰、膝のこの3つは、具体的に押しを加える時に非常に重要になってくるポイントです。
押しが主の場合と、ロッキングの場合とでは方法が違うので、次の様に分けて見ましょう。
|
|
[瞬間的な押し] |
[ロッキング] |
|
足 |
左足の内側の部分で地面に固定し、右足の爪先、または内側部分で地面に固定する |
左右の足を横に平行に広げて、足の前の方の内側部分で地面に固定する |
|
腰 |
腰は、肩より低い位置で入り、背中の線が20度前後、膝と足首の線が20度前後になるように沈む |
腰は、肩より低い位置で入り、足全体が背中の線から30度前後になるように沈む |
|
膝 |
120度前後に保つ(ためを作る) |
真直ぐに伸ばして保つ |
スクラムを組んだ後から腰を沈めることによって、膝に十分な「ため」を作ることが目的の様です。
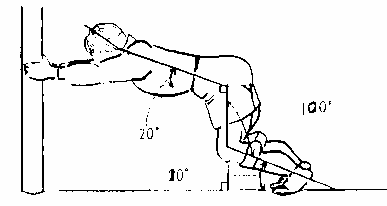
3 スクラムの組み方 Set Mcthod of Scrum
(1) フロントロー Front Row
ア フッカー(Hooker)は、両手を上げて両プロップ(Prop)の肩越しに腕を回しバインド(Binding)する方法と、フッカーが両プロップ脇の下から腕を入れてバインドする方法が有りますが、けっしてフッカーの脇腹でジャージと短パンを一緒にバインドしないこと。この位置でバインドしてしまうと、フッカーが非常に動き難くなるからです。
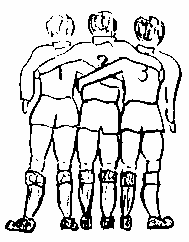
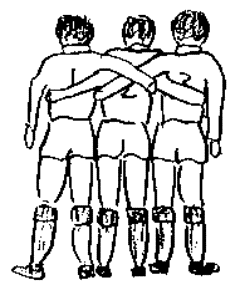
味方ボールのスクラムの場合は、左プロップが先にフッカーにバインドし、相手ボールの場合には、右プロップが先にフッカーにバインドする様にすると非常に良い。
この様にすると味方ボールの場合は、左プロップ(1)とフッカーがより密着でき、また相手ボールに対しては、フッカーと右プロップ(3)が密着することができて有利なスクラムワークを展開することができる。
両プロップの腕は、確実に締め上げ緩みが全く無いようにすべきです。
プロップのバインドを強調するためにスクラムの練習の時、先ず右プロップがフッカーの左側に立ってフッカーのジャージの胸部を左手で捕まえたまま、ぐるっと半周してバインドする様にすると本当にきついバインドを体験できるでしょう。常にこの様な強力なバインドをプロップに要求することが大切です。
イ フッカーは、両プロップの肩に腕を掛け、両プロップの脇の下あたりにバインドすることが望ましい。
この様にすると、相手の押しに対してフッカーだけが押し戻されてしまうと云うことが無くなるでしょう。
もしフッカーがもっと自由に動き回りたいと云う場合には、もう少し腕の位置を下げてもよいが、グリップをする位置が必ず両プロップの外側の脇の下でするようにすることです。
ウ この様にして、互いに強固なバインドしたフロントロー陣がスクラムを組むのですが、その場合には先ず正しいフット・ポジションを取ることを忘れない様にしなければならない。
この正しいフット・ポジションは、最初慣れない間は非常に不安定な感じがするかもしれないが、何回も何回もスクラムを組み練習を重ねているうちに次第次第に安定したものになってくるでしょう。
先ず左プロップですが、両足を広く開き、左側の足をやや前方に置き、そしてその足は内側の部分で地面に固定して、やや内側の方向に力を加え、後方からの押しを真直ぐ伝える様にすることを望みます。
また右側の足は、フッカーの左足のやや後方に置き十分なチャンネルを作り出す様にするのが大切です。
これに対して右プロップは、両足を後方に置き、自分が十分に安定するだけのスタンスを取ることです。ただしフッカーの足の位置に注意をよく払うこと。
フッカーは、自分の体重を左足で支える様にし、右足でのフッキングが容易にできる様な姿勢を作ることです。
この様にしてフロントローは、最良のフット・ポジションでロックの押し易い姿勢とロックの押しを前に伝えられる姿勢を取り作ることが最も大切です。
フロントローは、フッカーを中心に強固なバインドと正しいフット・ポジションから、3人の力が首筋の右側にそして左脚にしっかりと力を加え保ち、後方から来る押しの力をやや右前方の方向に伝える様にする。
(2)ロック Lock
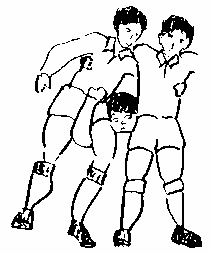
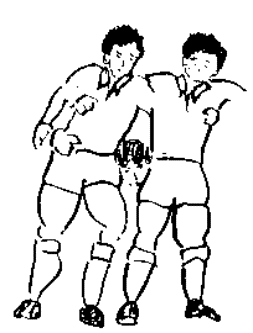
フロントローがきちんとスクラムを組むことができたら、次はロックの番です。両ロックに関して云えることは、より大きい身長のプレーヤーを右ロックに置くほうが良いです。
スクラムは、普通に組んで押せば、だいたい右側がじわっと押し込まれて左方向に回転していく傾向があるので、右側により重いプレーヤーを持ってきてその押し込まれて回る傾向を防ぎ、むしろ逆に押し込みたいのです。・・納得でしょう。
ア 先程と同じ理由で、右ロックの押しを強力にするために右ロックは左ロックの上からバインドし、左ロックの肩が右ロックの下になる様にすることが望ましいでしょう。
この様にすると、味方ボールの場合に右方向からフッカーにも押しを加えることができて、フッカーをよりトンネルに近づけることができる様です。
イ 両ロック同士のバインドの位置は、脇のすぐ下か、あるいはジャージと短パンの合さった付近を握るのが望ましい様です。
前者のバインドの方法では、フロントローおもよくバインドすることもできるし、後者のバインドの方法では、両ロックが押すときにしっかりと共にバインドすることができるでしょう。
ウ 両ロックは、先ず両フロップとフッカーの膝上部と腰の間あたりに頭を入れることです。 そこに頭を入れて、その頭を上の方に持ち上げる様にして、外側の肩がプロップの背骨の中心に当て、腰、脚の付け根でこれ以上は上に揚げられないと云う位置、 つまり最も安定した位置で止める様にする。
その位置こそ押しを加えるに最も理想的な押しのポイントとなる所です。
スクラムに入る時には、常に背中を真直ぐに保ち、しかも水平に保たれていなければならないし、そしてより低く、より強く押す力を出し伝えることのできる様に背中が安定していることが非常に大切です。
エ 外側の腕は、プロップの股間を通してプロップの前方でジャージと短パンを共に、または股間を通した手で自分の頭をつかみに行くようにバインドする。
または外側の肩と腕でプロップのお尻を抱え込んで、折り曲げた足の付け根の上からバインドする。
オ 両足は、後方に伸ばし肩幅あるいは肩幅よりやや広めにスタンスを取り、外側の足がプロップの背骨の中心の延長線上に来る様に位置する。
もし右側のロックの方が足が長かった場合には、右ロックは左ロックの右足に覆いかぶさる様にして自分の左足を置けばよい。
足、膝、腰は、「瞬間的押し」の姿勢にするか、「ロッキング」スタイルの姿勢にするかによって変わってくる。
(3) フランカー Flanka
両フランカーは、先ずプロップの腰骨の所に真直ぐに押しを加えられる様に内側の腕、手でロックの体に廻しバインドした姿勢でスクラムに参加する。
右フランカーの場合には、右ロックのかなり前方の部分にバインドし、押しの効果が最大限に得られる様に真直ぐにスクラムに入る様にする。
これに対して左フランカーは、左プロップの要求に従ってやや入る角度を変える必要があります。従ってバインドする位置も左ロックの前方ではなく、短パンとジャージの合さつた位置が良いでしょう。
勿論、左フランカーもできる限り真直ぐ押すことが前提ですが、味方のSHを保護するためにややお尻を外に開いた組み方が、多く用いられている様です。
しかし、そのために前方へ押すと云うことを忘れてしまつては本末転倒ですよ。
何れにせよ両フランカーの足は、後方で十分なバランスとパワーが得られる様に前後に開かれていなければならないでしょう。
そして両フランカーのスクラムでの第一の役割は、先ずは押すことです。
そのためには、スクラムを組む以前にプロップに肩を付け、ロックにバインドしてスクラムを組むことでしょう。
スクラムでは、押すと云うことをしっかりと頭に銘記してスクラムを組むべきでしょう。
左右のフランカーを決定する時には、より大型でタックルの優れたプレーヤーを左側にするのが望ましい。 この理由は、第一に大型プレーヤーを左側に持ってくることによって味方のSHを保護することができ、また相手のサイドアックが通常左側を攻めることが多い(防御側のSHが右側に出ている)ので、左側にタックルの強い、判断力の優れたプレーヤーをおいておくことが必要になる訳です。
(4) NO 8
ア NO8は、先ず頭を上げて両ロックを引き寄せる様にしてスクラムに入る。
この場合のバインドの位置は、両ロックの短パンとジャージの合さった位置で、足は後方に広げ最大の押しが加えられる様にスタンスを開いて取る。
イ 変形フォーメーションとして、NO8が右ロックと右フランカーの間に入ってバインドする方法や、左フランカーと左ロックの間に入ってバインドする方法がある。
前者は、スクラムを押し込むのに有利であり、相手ボールに用いると良い、またサイドアタックを用いる場合にも有効です。
後者は、味方のSHを保護するために有利で、味方ボールに用いると良い。しかし、スクラムの押す方向には、くれぐれも注意して真直ぐ押して下さい。
スクラムの組み方
(1)Front row (3)Flanka
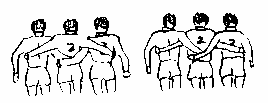
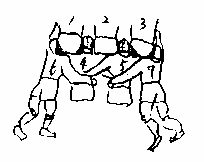
(2)Lock (4)NO8
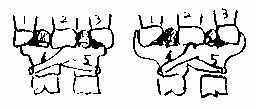

4 スクラムへの入り方
(1)バインド Binding
左プロップ(1)は、自分の左腕を相手右プロップの右腕の内側に入れて組む様にする。(自分の左大腿部の上に左腕を突っ張って組んでも良い)
左プロップの左腕は、相手に対しできる限り真直ぐ伸ばす様にバインドして、相手を強く押し込んだ状態でなければならない。
この様に相手を真直ぐにバインドすることによって、相手プレーヤーからの下方向へのプレッシャーに耐えることができる。そのためには、相手プロップのジャージと短パンの合さった部分か短パンの横の部分を左手で握ると良い。
右プロップは、自分の右手を相手左プロップの左肩の上に回して組む様にする。 しかし相手プレーヤーを下方向に押し下げた状態にならない様に注意する。
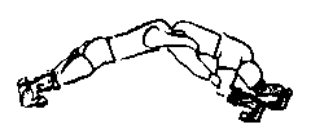
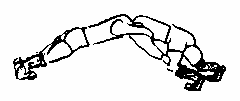
(2)高さ
ボールを投入する側のプレーヤーは、味方フッカーがボールをよく見ることができる様なスクラムを組む様にする。
反対側(相手)プレーヤーになったら、そうさせない様に努力することです。
従って、双方のプレーヤーの姿勢は、次の様になるでしょう。
ア ボールを投げ入れる側
左プロップ(1)・・・・前方向、前方向に押し上げ押し込む。
右プロップ(3)・・・・スクラムを安定させるために前方やや右側方向に低く組み、やや右側に押し出してスクラム全体の方向が真直ぐ(やや右側出る)に行く様にして、味方フッカーの足が出し安い様にする。
イ 相手側ボール
左プロップ(1)・・・・真直ぐ、やや内側に押しを加え相手右プロップが低く入って押して来るのを防ぐ。(やや押し込むと相手フッカーの足が出し難くなる)
右プロップ(3)・・・・やや押し下げる様に(潰れないこと)組み、相手の左プロップを不利な体勢(低い姿勢)になる様に持ち込む。
何れの場合でもフッカーは、両プロップをリードして味方の押しの効果が確実に相手に伝わる様に、可能な限り低いスクラムを組む様に努力することです。
(3)順序
フロントローにとって最も大切なことは、相手よりもポイントに早く集まって体勢を整え、できる限り低い姿勢を作りスクラムを組む。そうすることで、相手プレーヤーの下から入ることができ、より有利な姿勢を取ることができるでしょう。 次に大切なことは、スクラムの形、姿勢を崩さないことです。
そのためには、フロントロー陣が一つのユニットとして一体となってフッカーのリードでスクラムを組むことが非常に重要です。
実戦ではフッカーは、右プロップ(3)からやや早めに組んで行く様にリードし、真直ぐやや右前の方向に入る様にして右プロップがより良い姿勢でスクラムが組める様にし、しかも自然発生的な左方向へのホイールの動きを止め、相手フッカーを押し込めば投げ入れられるボールへのフッキングがたやすくなるし、スクラム全体で押し込むことができるでしょう。
(4)調 和
最後の大切なポイントは、8人で一体となってスクラムを組むことです。
フロントロー陣が相手フロントロー陣と接触する瞬間までには、味方のロックやフランカーが正しいスクラムのポジションにつくこと、でないとプロップが左右に割れたり姿勢が悪くなったりしてスクラムの効果を失ってしまうからです。 先ずフッカーが、より早く正しいポジションに位置し、それに集まり、フッカーのリードで8人が一体となって一歩前に動きスクラムを組んで行くことです。
スクラムは、この組む段階での8人の調和が極めて重要です。
一旦スクラムを組んでから再調整をしたのでは、8人が一体となってスクラムを組んで行ったメリットが失われてしまいます。
特に足の位置に注意すること、万が一スクラムを組んでから再調整をしなければならない場合には、敏速かつ素早く調整をすること。
(5)チャンネル
次に問題となるのが、スクラムの中でのボールの通り道、即ちチャンネルです。
一般的には、次の3つのチャンネルが用いられています。
ア チャンネル 1
左プロップ(1)と左ロック(4)の両足の間を通って、NO8から出されるチャンネル。
スクラムが安定してしっかり組まれていれば、左ロック(4)が左足を少し横に動かすことで、このチャンネルのボールの通り道を作ることができる。
このチャクネルでは、フッカーが思い切って速いボールを後方に送り、NO8がボールコントロールして出しても良いし、ボールを止めて素早く離れてピックアップしてサイド攻撃に転じても良い。
イ チャンネル 2
左プロップ(1)の両足の間を通り、左ロック(4)と左フランカー(6)の間を通ってボールが出てくるチャンネルです。
このチャンネルは、ボールが投入されてから出てくる迄の時間が最も短いボールの通り道です。
クイック・ヒール・アウトに用いると良い。しかし味方のSHに対して保護がなく、また時にはコントロールが非常に困難なボールが出てくることがあります。
このチャンネルからのボール出しは、是非マスターしておきたいプレーです。
ウ チャンネル 3
このチャンネルでは、右フランカー(7)が右ロック(5)の後方に下がってスクラムを組む3・3・2の組み方にして用いると良い。
ボールが投入されてから左プロップ(1)の両足の間を通って、右ロック(5)が左足を前に持ってくることによって両足の間をボールを通して、最終的にはスクラムの最後尾に居る右フランカー(7)へボールを送る。
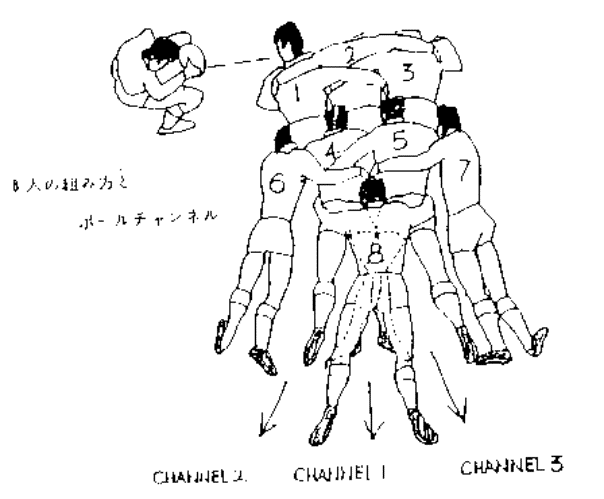
このチャンネルでは、味方のSHを保護し、SHによるサイド攻撃に転ずることもできる。
6 ボールの投入
実際にボールを投入する前にSHは、次のようなルールに対して明確な知識を持っていなければならない。
(1)SHは、自分の足首と膝の間でボールを保持して、スクラムが組まれたら遅れることなくボールを投入しなければならない。
(2)ボールは、フロントローの肩の線に沿って前方へ一回の動作で、速やかに投入されなければならない。
(3)投入されたボールは、味方の左プロップ(1)の左肩を越えた地点に直ちにグランドに接しなければならない。
ボールを投入する側のスクラムは、次の2点で相手チームよりも有利です。
第一にフッカー(2)が相手チームのフッカーよりも、よりボールを投入される位置に近い位置に居ることです。
第二に味方がボールを投入するので、ボールを投入するタイミングが分かっていると云う点です。
これは、SHとフッカーが練習を積むことによって、より効果を達成することができるでしょう。
実際によく行なわれる方法は、先ずフッカーがフッキングの準備ができたら、バインドしている左手をタップしてSHに準備「OK」を知らせる。
SHはそのシグナルを見て、例えばボールを保持している親指をボールから離しておき、その親指がボールに接したらすぐにボールを投入する等のシグナルを作るとか、フッカーに声でのタイミングを合わせるのも良いでしょう。
何れにせよボールを投入する側は、ボールをできるだけ早く投入すればするだけ、相手よりも有利に立てることでしょう。
また相手チームが押しの体勢に入っていない内にボールを投入し、ボールをフッキングするのも重要な作戦の一つでしょう。
ボールが投入された場合には、フッカーの足とボールが最も広い面積に接することが必要です。このためには、ボールの右端をスクラムの方に少し出して、つまり両手でスクラムと平行に保持していたボールを右手を少し出しボールをやや斜めして真直ぐ投入する方法を用いれば良い。
SHは、くれぐれもナットストレートにならぬように注意して下さい。
7 スクラムの応用プレー
スクラムでのバインド方法、足の位置、押し方、組み方、ボールの投入、フッキングの方法を見てきましたが、実際には基本のスクラムに対して、幾つかの応用プレーが存在します。
その前に、先ずスクラムの目的をしっかりと把握しておく必要があります。
ではその目的は、次の様に要約できるでしょう。
「スクラムでは、相手チームに最大限のエネルギーと押しの力を加えることにより、味方ボールのスクラムで生きたボールの獲得を目指し、相手チームボールに対しては、相手が生きたボールを獲得するのを否定することです。」
以上の様な目的を達成するために、実際には5つの戦法のどれかが用いられていることでしょう。
(1)フッカーがボールをかき取り出す。
(2)スクラムに8人全員で押しを加える。
(3)スクラムをできる限り低くし押して、相手フッカーのボールのフッキングを困難にする様にする。
(4)スクラムをロッキングする。
(5)スクラムをホイールする。
これらの戦法が少しずつ重なり合って実際には用いられている訳です。
例えば、相手ボールのロッキング・スクラムに対して、少しスクラムをホイールさせて相手のロッキング体勢を崩してから、8人全員で力を加えて押し込む。
この動きに出る前にスクラムをできるだけ低く組んで行く様にする。
これに対して味方のプット・インでは、余り多くの応用プレーは期待できないでしょう。せいぜいスクラムをロッキングするぐらいではないでしょうか。
これらの応用スクラムについて検討して見よう。
[1] フッキング
フッキングは、次の3つの動作から成立している。
第一番目は、フッカー自身が準備体勢を作ること。
第二番目は、実際にスクラムを組むこと。
第三番目は、実際にフッキングすること。
これらの3つの動作がしっかりできなければ、完璧なフッキングは不可能です。
(1)フッキングの準備をする
先ずバインディングですが、フロントローがバインドする際には、どの順番にバインドして行くかと云うことが有効なスクラムを組む上で極めて重要です。
フッカーとプロップとの横のバインドと共に、ロックとプロップとの縦のバインドも非常に重要です。
実際には、左プロップ(1)とフッカー(2)がかなり強固なバインドをするために左ロックの頭の位置にいろいろと工夫しなければならない様です。
もし味方のフッカーがスピーディーなフッキングで勝負するタイプのフッカーで有れば、左ロックの頭や肩がフッカーのお尻に当たっていてもよいでしょう。
これに対して、味方フッカーが相手フッカーの体勢を崩してフッキングするタイプのフッカーで有れば、味方フッカーにより自由な体勢を与えるために左ロック(4)は、左プロップ(1)のお尻を通して後方から背骨に対して押しの力が加えられるべきです。この押しが非常に有効にフッカーを助けることになります。
(2)スクラムへの入り方
スクラムへの入り方次第で、有利なスクラムを組むこともできるし、不利なスクラムを組まされることにもなるでしょう。
プロップは、組む前体重を「かがと」置き沈み込み、組むとき「かがと」から「つま先」へと体重を掛けながら組んで行く。
有利なスクラムを組むためによく用いられる方法として、フッカー(2)左プロップ(1)と共に右肩をやや落し気味にしてスクラムを組んで行く。この様にしてスクラムを組むと、相手のフロントローの首にプレッシャーを加えることができるからです。
左プロップとフッカーが共同して、相手の右プロップ(3)にプレッシャーを加え掛ければ相手からの押しをおさえ、相手フッカーをボールから遠ざけることができるでしょう。
相手ボールのスクラムでは、当然相手チームも同様な戦法でくることでしょう。
これを防ぐためには、ボールを投入される側の方に向かってできるだけ相手の首に入る様にして行くことでしょう。
(3)フッキング
フッキングと一口に云っても、味方ボールのスクラムと相手ボールのスクラムでは全くテクニックが違ってくる訳ですが、ではそれぞれの場合を検討して見ましょう。
味方ボールのスクラムでのフッカーは・・・・
ア ボールのプット・インのタイミングを予め知っている。
イ 相手フッカーよりもボールに近い位置に位置している。
ウ フッキングの瞬間には自分のウエートを相手に掛けられないので、非常に不安定である。
以上の3点が明確なポイントです。
一方、相手ボールのプット・インに対してのフッカーは・・・・
ア プット・インのタイミングが分からないのと、ボールへの位置が遠いと云う理由により、ボールを取るのに極めて不利な位置に有ると云えるでしょう。
イ もし、ボールを取ろうとしなければ、相手フッカーに比して多くの応用動作が可能になるでしょう。
フッカーが左右どちらの足で、フッキングするかと云う問題に関しては多くの議論が有るが、今日では様々な理由で遠い方の足、即ち右足でフッキングするのが、一般的になっている様です。
右足でフッキングする時には、相手から激しいプレッシャーを加えられると、右足を地面から上げ難いと云う点が有りますが。これもフッキングをする瞬間にフッカーが、自分の骨盤をボール投入の方向に回転させる様にしてフッキングを行なえば、右足を浮かし出すことができるでしょう。
これに対して相手ボールの投入に対しては、普通はボールに近い方の足、即ちこれもまた右足でボールをフッキングに行くことが多い様です。
この様にして相手ボールの投入と同時に右足を前方に出し、足首を伸ばして相手ボールを取りに行く、この動作を行なうにはかなりのテクニックとスピードが必要となるでしょう。
この様に相手ボールに対して足首を伸ばし足を出すと云う動作は、極めて不自然な動作となることでしょう。
だからこの様な足首や爪先の柔軟性は、日常的な練習の中から生まれてくることでしょう。
味方ボールにせよ、相手ボールにせよ、フッカーは日常的に自分の足腰をよく鍛えると共に、フッキングの練習をしっかり行なっておくことが大切です。
フッカーがよくSHとフッキングの合わせ練習をしているのを見受けますが、実際にはコンビを組むSHが近くにいなくても、フッカーはフッキングの練習にもっともっと精出して行なって欲しいものです。
地道に練習するか、しないで「私は代表選手だった」いや「私は代表選手になれなかった」と云う、大きな差を作り出すことになるでしょう。
ラグビー場に行かなくても、グランドに居なくても、何時でも何処でも暇と機会を見附だしてフッキング練習に精を出すべきでしょう。
栄光の「2番」のジャージを着たいのなら、やるべきです。
[2]ロッキング スクラム(The Locking Scrum)
ロッキングは、味方ボールを確実に獲得しようとする時に用いられるスクラムテクニックです。押されないスクラムと云うことかな。
味方ボールのスクラムでボールを獲得しようとする時には、フッカーがフッキング体勢でいるので相手チームの8人による押しに対して7人では耐えきれない場面が起こりうることでしょう。
そこでこの相手チームからの押しに対抗するために用いられるテクニックがロッキングテクニックなのです。
ボールが投入される迄は、先ず8人で組み押して相手スクラムにプレッシャーを加え、ボールを投入する瞬間にフッカーを除く残り7人が「押し」から「耐え」に転ずるが、そのタイミングが非常に重要なのです。
ボールを投入する側は、そのタイミングを知っているので相手より有利にこのテクニックを用いることができるのです。
相手にスクラムを最初から押し込まれた状態ではこの様なテクニックは使えませんので、どうしてもロッキングに入る直前までは8人全員で相手スクラムに十分なプレッシャーを掛け続けておくことが大切です。
ロッキングのための姿勢は、基本的には両足を後方に置き、両膝を伸ばし、両足を直線平行にして、腰を低く沈めるのがその特徴でしょう。
スクラムでのこのタイミングの習得は、数多くスクラムを組む練習からそのテクニックが生まれてくることでしょう。
効果的なロッキング・スクラムを得るためには、次の順序でコールして実施すると良い。
「ロッキング・コール」 Locink Call
(1)スクイーズ (Squeeze)
先ず8人でスクラムを押し込める様に膝を曲げ、このコールでバインドを強固にする。
(2)ステディー (Steady)
このコールで背中が地面と平行になる様に、一気に膝を伸ばす。
できれば膝を伸ばした時に自然に上体が前に出るくらいになればよい。
(3)シンク (Sink)
ボール・インと共に全員が膝を伸ばしたまま、更に体を低く沈める。
コールは、常に上記の順番でコールして行なうこと。
これらの一連のロッキング・コールのシグナルを出すのは、左フランカーかまたはフッカーが出すのが最適のポジションでしょう。
一番目の「スクイーズ」は、スクラムを組んだ瞬間からコールを繰り返し云い続けて「バインド」を強固にさせることが大切です。
二番目の「ステディー」コールは、ボール・イン直前にフッカーから左プロップに対して出されるシグナルに供応して用いると良いが、もし左フランカーがリードする場合には、左プロップが膝を下げる動作に合わしてコールを出せば良い。 三番目の「シンク」コールは、練習で身に付けたタイミングでSHの「ボール・イン」と共に用いると良い。
[3]相手ボールに対する8人の押し(The Eight man shove)
相手ボールのプット・インの場合に用いるテクニック。
ボールインの瞬間には、相手チームのフッカーが押しに参加していないことが多く実質上7人になるのに対し、こちらは8人で組み押し込むことによってその体重差を有利に用いて押し込む方法。
従ってこれは、相手ボールのプット・インに対して、相手にクリーンな生きたボールを出させないために用いられるテクニックと云えるでしょう。
この8人の押しの効果について具体例を挙げて考えて見ましょう。
例えばAチームとBチームの試合で、スクラムが合計20回組まれ共に10回づつのボールを投入したとする。
そこで次の3つのケースについて考えて見ます。
(1)Aチームが10回の生きたボールを出し、またBチームも同じ10回の生きたボールを出した場合。
(2)Aチームのフッカーが相手ボールを取りその結果13回生きたボールを出し、Bチームが7回の生きたボールを出した場合。
(3)Aチームが8人での押しに徹して相手にクリーンなボールを出させないようにして、Aチームが10回の生きたボールを出し、Bチームが10回とも「死んだボール」を出した場合。
この様に考えて見ると、結果は歴然としてくるはずです。だから大切なことは、相手チームに生きたボールを出させないと云うことでしょう。
これこそ8人での押しに対する基本的な考え方でしょう。
8人の押しも、ロッキング・コールの要領でコールして行なえば基本的には共通した押しができるでしょう。
相手チームのボールでは、ボールを投入するタイミングが分からないので、ボールの投入に押しを合わせることが非常に困難となるでしょう。
もしコールを掛けて相手ボールを押すのであれば、その声を掛ける最適のポジションは、相手のSHに近いポジションにいる右フランカーでしょう。
(1)スクイーズ Squeeye
このコールで互いにバインドを締め上げて、強固にする
(2)ステディー Steady
このコールで腰を低く下げて、膝に一層のゆとりを作る。
(3)ナウ Now
このコールで激しく膝を伸ばして突き上げる、8人全員が「ナウ」と声を発して押す。
この声によって8人がユニットとして働くことができ、相手チームのボールコントロールが難しくなることでしょう。
相手スクラムを押し込む(動き出す)までは足を小刻みに激しく前後に動かし、一旦スクラムが動き出したらゆっくりと真直押しスクラムを潰さない様にし前進し続ける様に押すことが大切です。
この8人の押しを有効に使うと、味方フッカーがボールを取りに行かなくても結果として相手ボールを獲得することができるでしょう。
これを更に有利に進めるためには、初めから低いスクラムを組み相手フッカーのフッキングが困難になる様にする。
低い姿勢のスクラムを組むことは良いが、絶対に潰れないこと。
[4]ホイール (The Wheel)
ホイールは、味方ボールにおいても相手ボールにおいても、用いられるテクニックです。
ここでは、味方ボールと相手ボールの場合に分けて検討して見ましょう。
「1」味方ボールでのホイール
味方のスクラムが相手を圧倒している場合、また味方チームが相手スクラムを支配していない場合でも、8人が一体となってホイールを行なわないとホイールの効果は、期待薄になるでしょう。
従って味方ボールのスクラムでホイールする場合には、相手を押し込んでホイールする、また相手が押し込んできたらその出鼻を捉えてホイールし、おもに相手陣内で用いるべきでしょう。
もしボールコントロールに失敗してカウンターアタックをされても、それほど大きな影響を受けない位置で用いるべきでしょう。
味方ボールでのホイールは、現在あまり積極的には用いられていないので、スキルを向上させて実施すれば効果は大いに期待できる。
ルール上90度以上スクラムにボールを保持して回転すると、スクラムは組み直しとなる。
味方ボールのホイールに於けるキーファクターは、次の4つです。
(1)右回転(時計回り)へのホイール
スクラムで自然発生的に起きる回転をホイールの動きに利用する。
(2)プレッシャーの適用
スクラムの回転を開始させるためにプレッシャーを有効的に適用する。
ア スクラムを押し込んで、相手がその押しを持ちこたえ、耐えた瞬間か゛ホイールに入るタイミングです。
イ 相手の押しを食い止めた瞬間が、ホイールに入るタイミングです。
(3)ボール保持
ボールを確実にコントロールする。
(4)ドリブル・アウェイ
ボールを足でゲインラインの前に持って行く。
これらのキーファクターを個々に検討して見しょう。
(1)右回転(時計回り)へのホイール
スクラムの基本的な組み方からも理解できる様にスクラムは、そもそもスクラムを押し合えば時計回りに回転する傾向を持っています。
従ってホイールする場合には、この自然の傾向を大いに利用して行なうべきです。またこの動きに反する方向にホイールをさせることは、非常に労力とスキルを要することでしょう。
(2)プレッシャーの適用
ホイールを開始させるためには、次の様な3種類のプレッシャーの適用があります。
第一には、8人全員が一歩前に押し込んでから左方向に回って行く方法。
第二には、左プロップ、左ロック、左フランカーの三角形の“くさび”で相手を真直ぐ押し込んで行く方法。
第三には、左プロップ、左ロック、左フランカーの三角形の“くさび”で相手の押しを食い止めてから行なう方法。
この方法で共通する項目は、次の諸点です。
ア スクラムの左サイドにいるプレーヤー即ち左プロップ、左ロック、左フランカーが真直ぐ前に押し、ホイールが始まったら押す方向を右方向へ移動する様に押し込んで行くこと。
イ フッカーが自分を中心にして、味方の左プロップを前に右プロップをやや後ろに引き回す様にリードして回すこと。
ウ 右フランカーが、ホイールが始まる様に、押しの方向を左やや後方へ右プロップ、右ロックをリードし、NO8を横からサポートに行くこと。
エ リーダーは、FW8人全員にボールが投入される前に、ホイールを開始するコールサインを知らせ実施するタイミングを徹底しておくこと。
(3)ボールの保持
ホイールを行なう前に、NO8かロックのポジションでボールをキープしてからホイールに転ずること。確実にキープしていないと不成功に終わる。
(4)ドリブル アウェイ Dribble Away
左プロップ、左ロック、左フランカー3人での三角形の“くさび”で真直ぐやや右側への押し、NO8が自らキープしたボールをドリブルしながら左斜め前方に運びゲインラインに向かう。
NO8の左サイドをSHが、右サイドと後方を右フランカーがサポートして前進する。その前にボールをNO8が確実にキープし、スクラムを一呼吸安定させてからホイールに入りドリブルして行く。
ドリブルアウェイに転じたらボールコントロールを確実に行いながら前進する。
危ないと思ったら自らセービングしてでもボールを確保していくこと。
右回りで左のドリブルウェイを前進すれば相手SHがすぐ妨害にくるよ。
「2」相手ボールのスクラムでのホイール
相手ボールにおけるスクラムでのホイールは、次の様な場合に有効です。
(1)味方が相手ボールのスクラムを支配している時。
(2)8人の押しが相手スクラムに効果がない時。
(3)相手ボールを全く獲得できない時。
(4)相手が右オープン攻撃に出ようとした時。
相手ボールのスクラムに対して行なうホイールは、味方の8人の押しや、フッカーが相手ボールを取りに行く時や、相手のオープン攻撃へのディフェンスにと並行して補助的に用いるべきでしょう。
理想的には、相手陣内のゴール前10〜20メートル付近のスクラムで用いると有効です。
そのキーファクターは、次の4つです。
(1)右回転(時計回り)へのホイール
(2)プレッシャーの適用
(3)左フランカー、NO8、右フランカー(サードロー)の離れる時期
(4)ドリブル アウェイ
これらのキーファクターをそれぞれ個々に検討して見ましょう。
(1)右回転へのホイール
これも先に指摘した様に自然発生的に起きるホイールの方向を利用する考え方をする
(2)プレッシャーの適用
これも先に説明したテクニックと同じですが、次の様な点が異なります。
ア ボールが投入され、スクラムを押す、力が一呼吸均等した瞬間に開始する。
イ ボールが投入されると同時にホイールを開始する。
しかしボールが投入される前にFWリーダーがサインを出しておく必要が有るし、コールサインを出すのは右フランカーが良い。
(3)サードローのスクラムから離れる時期
スクラムからボールが出るまで離れることはできない。
相手ボールへのホイールは、サードローがスクラムからボールが出るまでスクラムから離れることが出来ないので、非常に危険である。
(4)ドリブル アウェイ
理想的には、相手チームがプレッシャーを受けてスクラムでボールのコントロールを乱してくれることです。
そこで味方SHが相手チームのスクラムの周辺にこぼれ出たボールを足で引っかけ、更にNO8や右フランカーと共にプレッシャーを掛け続けて、こぼれ出たボールを足で処理する代わりにセービングしたり、ボールを地面から拾い上げてスクリーンパスで攻撃に転ずることもできるでしょう。
「3」ホイール対策
味方ボールをホイールされた場合には、次の3つの方法で対処する。
(1) キングした直後、スクラムの押しを全員で鋭く右の方向に移動させる。
(2)相手チームにホイールをさせて、味方のロックまたはNO8からボールをキープしたままドリブルアウェイのテクニックを用いる。
(3)ホイールが始まったら、NO8が素早くボールを拾い上げてスクラムを離れて、SHか右フランカーにスクリーンパスして攻撃に転ずる。
スクラムでフロントーの3人が強ければ、スクラムが安定する。
スクラムでロックを含む前の5人が強ければ、スクラムをコントロールすることができる。
そして、サードローの3人が走れば、FWが走る強力FWとなるでしょう。
スクラムでそのゲームの勝負が90%決まりです。
先ずスクラムを強くしてゲームに臨みましょう。
