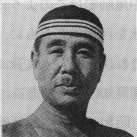
(6)中尾 保師範と能島流浜寺水練学校
能島流を伝える浜寺水練学校の歴史は、故中尾 保師範の存在を抜きにして語ることは出来得ないものであり、この欄では能島流を今に伝えた最大の功労者である中尾師範について述べることにする。
中尾師範は周知の通り、日本水泳連盟の歴史上にとっても、戦前国際水泳連盟への日本の加盟を調印するなど、日本水泳連盟発展の功労者として知られているが、浜寺水練学校へは、明治39年毎日新聞社が主催した当時の浜寺水泳場開校の時、12才で入門された。この時の初代師範は小池流の井上富蔵氏であった。
大正8年、先生25才の時には浜寺水練学校師範となり、また能島流17代宗家多田一郎先生より直接能島流秘伝を伝授され、能島流師範ともなられた。大正11年に、浜寺水練場は「浜寺水練学校」と改称された。
当時の時代背景は、海国日本の民族は国民皆泳を目指す指導者が全国に広がっており、日本泳法各流派はそれぞれの地に於いて水泳の指導に当っていた。又外国からはクロール、ブレスト、バック、等の泳法が入ってきており、浜寺水練学校としては、中尾師範が能島流を主流に小池流を始め日本泳法の各流派の泳ぎを取り入れるとともに、またクロールをはじめとした外来泳法も教科目として組み入れ子弟の指導に当たった。この様に流派の異なる泳ぎをーヶ所で教えるのは、当時としては浜寺水練学校しかないということで、全国から子弟が集まったと伝えられている。
その後、多田一郎宗家より中尾師範へ第18代宗家を引き継いで欲しいと言う旨の話があったが、中尾師範は「浜寺水練学校はいろんな泳ぎを教えて行こうと志す時、宗家を引き継げば何かと支障が起こりそうな…」と言う懸念がその当時にはあった為、「能島流師範として、泳法は引き継ぐが宗家はどなたか他の方にお願いして欲しい」と、堅く辞退されたと聞いている。
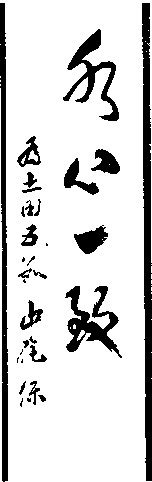
昭和9年8月1日甲子園水泳研究所10周年記念水泳大会で、日本諸流模範泳法に於いて、能島流第17代宗家多田先生(76才)は、抜手、捨浮を披露され、又中尾師範は浮き身十体、手足搦(二段絡み)を披露されたが、この泳法こそが多田先生から直伝の能島流の極意に他ならない。
中尾師範はこのように能島流の泳ぎを引継ぎ、尚かつ一流派にこだわる事なく国民皆泳を目指すとともに、日本水泳界の将来を見通し指導に当たられた。浜寺水練学校はそれ以後36万人に及ぶ子弟を生み出し、現在に至る迄85年の歴史を誇っている事は世間周知の事実である。
昭和38年、中尾師範が亡くなられ、その翌年の10月15日東京オリンピック記念日本泳法大会が芝白金のプリンスホテルプールで開かれた時、巽 忠蔵氏は能島流第18代宗家として「鯛泳ぎ」を披露され、浜寺水練学校からは中尾善宣氏(故中尾師範の次男)が「手足鰯(二段絡み)」を披露した。大会後、巽先生は中尾善宣氏と同行していた兄の隆洋(故中尾師範の長男で現浜寺水練学校評議員)に、能島流第19代宗家を譲る旨の申し出があったが、隆洋氏は「父の意志に反する事でもあり、浜寺水練学校は宗家を引き継がなくても実質“泳法"は引き継いでおります」という事で、故中尾師範の遺志を守られた。
しかしながら、巽先生としても高齢になられ、以後の能島流の継承の件については相当ご苦心され種々方策を検討された後、昭和45年に至り当時の浜寺水練学校師範である高橋清彦氏に継承の願いがあり、高橋先生は巽先生から能島流第19代宗家を譲り受けることになった。その後、昭和61年、澄田奈良夫が浜寺水練学校師範就任と同時に能島流第20代宗家を引き継いだ。
このように、故中尾 保師範は我が能島流浜寺水練学校にとっては欠かす事の出来ない存在であり、大正8年以来、実に45年の永きに亘り、能島流浜寺水練学校で指導にたずさわられ、国民皆泳と日本水泳界の発展に大きく貢献され、かつまた能島流は中尾師範の教えのご意志を継承し今に至ったものである。