平泳は、能島流諸術の基礎であり厳格な動作を要求される。

左右対称で、平体を保つ。
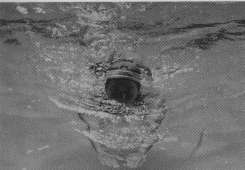
手は掻くことよりも浮きを取ることを主とし、五指は揃える。

能島流の、蛙足を用いる。

手足が揃ったときの伸びは良くとれていること。
(2) 能島主流遊泳術
| ① 平泳(ひらおよぎ) 平泳は、能島流諸術の基礎であり厳格な動作を要求される。 |
 左右対称で、平体を保つ。 |
|
手は掻くことよりも浮きを取ることを主とし、五指は揃える。 |
能島流の、蛙足を用いる。 |
|
|
|
|
② 抜手ーツ掻(ぬきてひとつがき) |
③ 抜手二ツ掻(ぬきてふたつがき) |
|
|
|
|
|
|
抜手合わせ
|
|
|
平体を保つ。 能島流の蛙足を用いる。 リズム感よく泳ぐ。 |
|
|
④ 立泳(太刀泳)(たちおよざ) |
||
|
|
|
|
|
前 進 |
|
|
|
側 進 |
|
|
⑤ 鰡 飛 (いなとび)
|
身体を飛び上げる前の動作 |
|
|
|
手で水を圧し上半身を飛び上がらせた後、水を後方に跳ねる。 |
|
|
|
腕は体側を通って前万にもどす。 |
|
|
⑥ 掻 分 (かきわけ) 鰡飛びの連続技である。
|
|
|
|
|
側 面 |
|
|
|
着 水 |
|
|
⑦ 舞 鶴 (まいづる) 立泳の姿勢から、掌を前に向け、揃える。 |
|
|
|
|
両腕を伸ばしたまま後方に回し肘を曲げる。 |
|
|
手の甲で水をはね両腕を斜め後方に高く伸ばす。 |
|
|
|
⑧ 静抜手 (しずかぬきて)
|
|
|
 手は親指と四指は離し、腕は前方まで運ぶ。 |
||
 |
||
⑨ 二ツ掻 (ふたつがき)
立泳の姿勢から、掌を下に揃え、一方の手は体側を通って斜め後方から水面上に抜き出し、脇が約45度の角度になるくらい腕を大きく回す。この時手先は、親指と四指は離し肘を少し曲げ、『蟹の爪』のごとく前方を向くようにしながら円形を描き、面前まで回し水中にいれる。片方の手は、水中で水を掻き押さえるように二度内側に小円形を描き、そのあと後方に伸ばす。
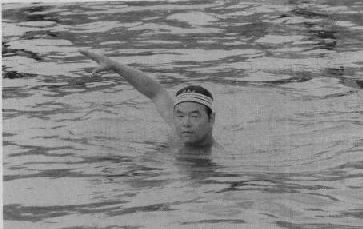
能島流の粋とされ、最も正確な動きを必要とされている。
|
⑩ 水入鰡飛 (すいりいなとび)
|
|
|
|
|
側 面 |
|
|
|
正 面 |
|
|
戦場で、偵察等に用いられた泳法。 |
||
|
⑪ 鴎 泳 (かもめおよぎ) 足は巻足を用いる。 |
|
|
|
|
手百を内側に動かし水をはねながら前進する。 泳ぎ終わりの際、手先で水を外側にはねる。 |
|
|
|
||
|
⑫ 伝 馬 (てんま) 手の力だけで泳ぐ泳法。 前進・後進・回旋・回転がある。 表 顎を締め、膝・足先を軽く付け、足先を水上に出す。 |
|
|
|
|
裏 脇を付け水面と平行方向に水を押さえる。 足の由を伸ばす。 |
|
|
⑬ 手足搦 (てあしからみ)
|
手足二段搦の縛り方 |
|
|
|
前進(裏向き) |
|
|
|
後進(表向き) |
|
⑭ 水 歩(すいほ)
水中を歩行しているような姿に見えるところから名付けられた。
立泳の変化したもので、類まで沈めてよい。両手は左右に開き、掌は下に向け、四指を付けて親指は内に屈める。足は、膝を大きく開かず、立泳の足、巻足を用いる。
⑮ 水 書(すいしょ)
立泳をしながら、筆と紙を持ち、文字や絵などを書く。
⑯ 瓜 剥(うりむき)
立泳の姿勢で瓜と包丁を持ち、貴賓席に刃を向けずに、皮を六片に剥く。剥いた後の身の切り方には、土用瓜(車切)、秋瓜(竪切)などの口伝がある。又、手に残った瓜を水に浮かべるのであるが、浮かべる際、花が漂っているかのように、六片の皮を上手に剥く。
⑰ 弓 術(きゅうじゅつ)
立泳の姿勢で弓を引き、弓を射るが、天に向かって構える場合『天弓』という。
⑱ 操 銃(そうじゅう)
水中で、銃を発砲する術である。
⑲ 沖の白帆(おきのしらほ)
頭に一本と左右両足の親指と第2指の間にそれぞれ1本の計3本の扇をつけ、回旋・回転を行う。
⑳ 鯱 泳(しゃちおよぎ)
沼または、浅瀬を泳ぐ際に通した泳法で、伝馬裏の姿勢(足首は曲げる)で前進する。
21 片手鰡飛(かたていなとび)
鰡飛を片手だけで左右交互に行う。
22 片手掻分(かたてかきわけ)
掻分を片手で、左右交互に行う。
23 鳧 方(かもがた)
体は伏し身で、両手は揃えて背部に回す正体と、手先を組み重ねて前に差し延ばす略体がある。足首を組み、折り曲げて踵を臀部につける。
24 竹具足泳(たけぐそくおよぎ)
甲冑泳の練習泳法で、腹部に砂袋をつけ、次第に砂の量を増す。次に胴衣股引の上に竹具足をつけ、手甲・脚群・木太刀・陣笠をつけて泳ぐ。
26 軍貝音入(ぐんかいねいれ)
立泳の姿勢で、片方の手は水上で軍貝を持ち、一方の手は水中で浮きを取り、法螺貝を吹き鳴らす。
27 浮き身(うきみ)諸体
o 捨 浮(すてうき)
浮き身の基本型で、身体は上向き、両手は掌を上にやや円形に成り、両足は自然に伸ばし足は開き、豚を少し曲げ浮く。
o 枯木流(かれきながれ)表・裏
表は上向きの姿勢、裏は下向きの姿勢で、手・足を揃え自然に伸ばす。
o安 坐(あんざ)
上向きの姿勢で座禅もしくはあぐらを組み、手は膝の上に置いて浮く。
o十字浮(じゅうじうき)
上向きの姿勢で、両手は横に伸ばし、足は揃える。
o槍 浮(やりうき)
上向きの姿勢で、両手を体側につけ、足はそろえて伸ばした型で浮く。
o横 浮(よこうき)
横向きの姿勢で、片方の手を手枕にして頭の下に当て、両足を捕えて、やや縮める気持ちで浮く。
o達磨浮(だるまうき)
両足を揃え、膝を曲げ、その膝を手で抱えた型で浮く。
o立 浮(たちうき)
立ったままの型で、手は体側に足は揃えて伸ばす。
o座禅浮(ざぜんうき)
上向きの姿勢で座禅を組み、手は腹部で組み合わせる。
o枕 浮(まくらうき)
手は頭の下で組み合わせ、足は座禅を組むものと揃えて伸ばす型とがある。
o大の字浮(だいのじうき)
上向きの姿勢で、両手を横に伸ばし、両足は豚を伸ばし広げて浮く。
o 筏 流(いかだながれ)
数人または数十人が連なって枯木流(表)を行い、筏の如く浮いて流れるものである。
連なり方には、前者の足首とふくらはぎを持つ方法がある。
o軽石流(かるいしながれ)
膝を折って両手で強く抱き、回転しながら水流に従って浮く。
28 潜水法(せんすいほう)
o底 息(そこいき)
比較的長時間水入りをなす為の術である。
o掻 伸(かきのし)
手は前に伸ばし、大腿まで掻き切り充分伸びをとる。足は蛙足・バタ足のどちらを使っても良い。
o蹴 伸(けのし)
水底を蹴って進む方法で、蹴ると同時に手で水を充分掻き、その姿勢のまま伸びをとる。
29 飛込術(とびこみじゅつ)
o 直 進(ちょくしん)
体は垂直のまま、両掌を局部に当て保護し、両足をそろえ足から飛び込む。
o鰹 落(かつおおとし)
両手を頭の両側から先に伸ばして手から飛び込む。
入水後、手を反らせ早く浮かび上がる。
o陣 笠(じんがさ)
少し前傾姿勢から、両腕は前に伸ばし、足は前後に開き、踏切ると同時に後方の足を前に出し、顔を没さないように入水する。
o中 転(ちゅうがえり)
右手は頭部の後ろに当て、左手を腹部に当てて、体は出来る限りまるく屈めて、前方に回転する。
従って高所からでは2回転、3回転してから水面に落ちる。